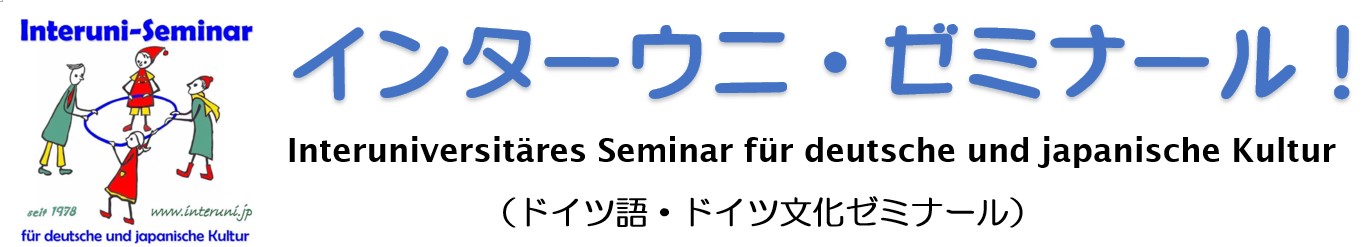2025年3月7日~11日、山中湖畔の『平和荘』で第40回の記念となる春のインターウニを実施しました。(今回の全体テーマや企画方針などについてはこちらの募集サイトをご覧ください。)
今回は高校生から社会人まで含む一般学生参加者が52名(うち6名が昨年に引き続いての参加)、ドイツ人学生(PraktikantInnen)が9名、教職員16名で、「平和荘」にぎりぎり入る人数でした。大雪と晴天が交互に訪れる中、ゼミは例年通り、語学力別のクラス分けとグループ授業、それから今年は全員でのPhonetik(発音)練習から始まりました。2日目になると、すでに互いに知らなかった学生たちとドイツ人学生の間にグループごとの連帯感が生まれ、3時間ずつのグループ授業5回は3日目に終了しました。どの授業も、大学では経験したことのないような創意工夫に満ちたものばかりで、学生からさまざまな発言を引き出し、単語を体系的に整理して使いながら覚え、ドイツ人学生にたくさん助けてもらいながらプレゼンを作ったりディベートしたりする180分の授業はどれもあっという間に過ぎていきました。



しかし単なる語学学校にとどまらないインターウニの本領発揮はここからです。今年のインターウニでは事前に参加者の皆さんに、私たちの近未来に向けて関心のあるテーマを選んで考え、また材料を集めてくるようにお願いしてありましたが、そうした関心に基づいてゼミでは新たに【環境】、【ルッキズム】、【育児・労働】、【人文学】、【AI】、【未来の生活】、【政治】、【移民】という8つのテーマ別グループが作られました。これらのテーマについて、ゼミ3日目・4日目には各グループで自分たちの問題意識や意見が話し合われ、ドイツ人学生とともに日独を比較しながら創意工夫に満ちたドイツ語のプレゼンが作られていきました。もちろんこれは、とりわけドイツ語を習い始めて1年目の参加者にとってかなり高いハードルでしたが、ドイツ人学生や上級生たちに助けてもらいながら、習い始めたばかりの言語で自分の知的関心を表現してみる経験を通して、今後のドイツ語学習で克服したい課題や目指したいスキルが具体的に見えてモティベーションを高めた人がたくさんいたことと思います。自分のドイツ語力でもいろいろなことが伝えられる自信を得られた人も、また大学の初級ドイツ語の語学授業などでは滅多に体験できないワクワクするようなドイツ語との出会いを体験した人も多かったことでしょう。学びたてのドイツ語を使って目一杯考え議論できることがインターウニの醍醐味です。



今年のインターウニではゲストとして、ジャーナリストとして日独のメディアで大活躍しているマライ・メントラインさんにお越しいただきました。グループプレゼンの準備がほぼ終了した4日目夕方に開かれたマライさんを囲む全員討論では、私たちの近い未来に向けて日本や世界が抱える問題や日本やドイツの社会に突きつけられている課題について、日本語とドイツ語を交えて活発な議論がなされました。日本では学生が日頃話題にするのを避けがちな政治や移民についての話題についても、(なぜ日本の学生が話題にしないのかについても含めて)大いに議論が盛り上がりました。どんなに楽しく盛り上がったかは、このページのトップを飾っている写真の参加者たちの表情からお察しください。

4日目の夜には盛大なSchlussfeierが開かれました。おとなしくクイズから始まって、椅子取りゲームやTopfschlagenなどでみんなお腹を抱えて笑い転げたあと、ピアノやギターなどの演奏、そしてプロ・ダンサーとしての長いキャリアを持つ日本人メンバーを中心に即席で結成された日独ダンス・チームによる圧巻の踊り「瀕死の白鳥&よさこい・ソーラン節」など、参加者たちの豊かな才能が次々披露されました。最終日には8つのグループのプレゼンが行われ、大いに盛り上がった今年のインターウニも無事に閉会を迎えました。



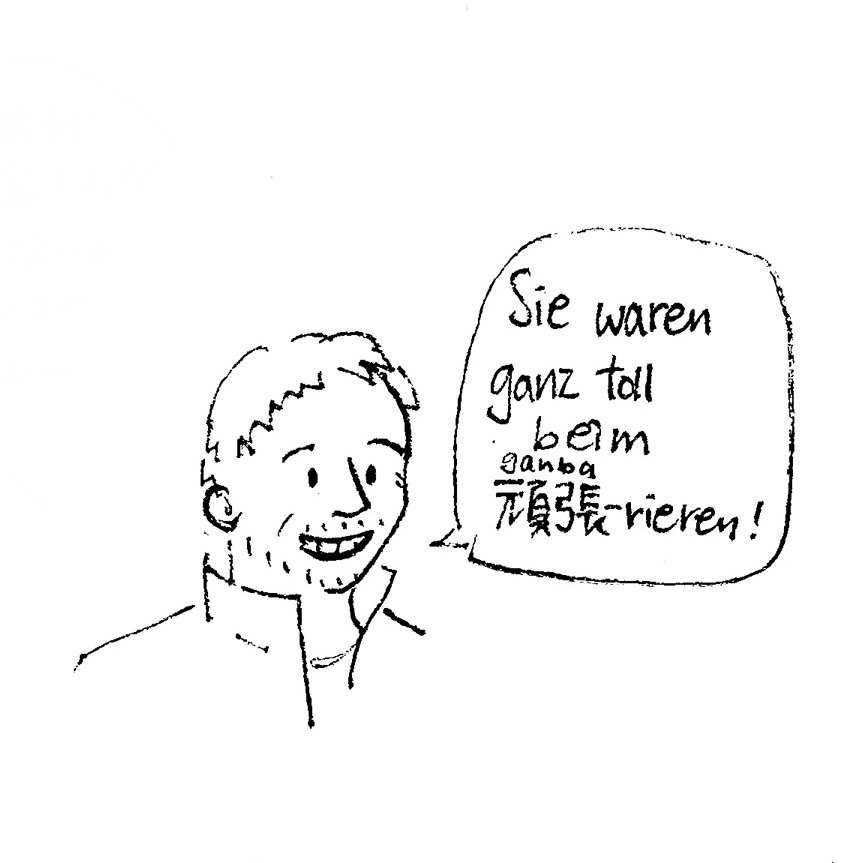
インターウニは、毎年異なる参加者が「どんなゼミだろう?」とこわごわ集まってくるにもかかわらず、必ずみんなが楽しく盛り上がってドイツ語を学ぶことになってしまう不思議なゼミです。それにしても今年の参加者はいろいろなことに真摯に向き合って考え抜くタイプのモティベーションの高い人が多かったようで、テーマ別グループを選ぶときに書いてもらったアンケートでも、ゼミ終了後に寄せられたアンケート(こちらのサイトにその一部を掲載してあります)にも長文レポートが多数寄せられて驚かされました。奇跡とも言える一期一会の理想的環境がインターウニを実施するたびに立ち上がるのは、参加者の皆さんが持ち寄るモティベーションと、ボランティアでご協力いただいている教職員の皆さんの熱意のおかげです。参加してくださった皆さんに感謝を込めながら、実行委員会としてはこの、知的に考えながらドイツ語を楽しく学べるインターウニの灯を消さないように、「未来に向けて」、また次のゼミを計画していきたいと考えています。